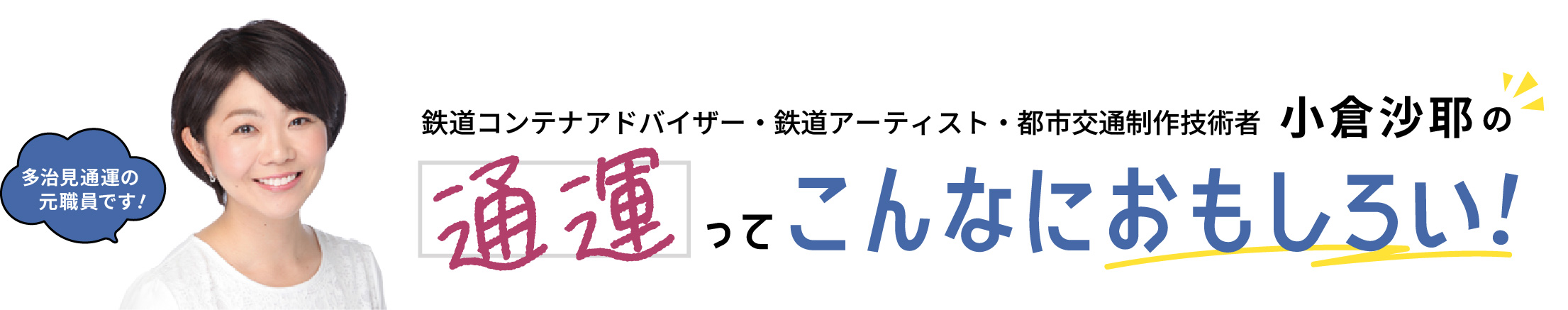【第99回】鉄道コンテナで備蓄?

BCPと鉄道コンテナ
鉄道コンテナ輸送におけるBCP対策については、これまでのコラムにて、貨物駅を利用してクロスドック輸送を行う訓練などについてお伝えしました。「BCP コンテナ」でインターネット検索をかけてみると、拙コラムがかなり上位に表示されていて、ありがたい限りです。
さて、鉄道に限らず様々なコンテナの利点といえば、床に直置きできること。廃コンテナが倉庫として利用されているのを見かけた方は多いかと思います。
通運事業も行われている別会社の話題になりますが、丸和運輸機関では昨年、BCP対策として、同社が保有する鉄道用クールコンテナを利用した新しい備蓄方法についての提案イベントを行いました。災害食としてコンテナ内に冷凍食品を備蓄して避難所の食事の質向上を図る提案や、GPSによるコンテナ管理と備蓄管理の実演を行ったとのことです。
長期間の留め置きは可能?
これはあくまで、冷凍食品を避難所まで「運ぶ」提案ですが、私は最初、現役コンテナを備蓄機能として利用する=長期間の留め置きを行うのかと見間違え、目から鱗でした。運送の提案であれば納得です。ただ、もしも鉄道コンテナを1か月間ほど留め置き、その後別場所に輸送、コンテナ内の物品は企業内や自治体においてローリングストック品として消費という流れを作ることができれば、新たな鉄道コンテナの需要が生まれそうです。課題は備蓄品としての物品をどう積むのか、そしてコンテナを長期間留め置くため発生する留置料、固定資産税などでしょうか。
実際に「ローリングストックコンテナ」として鉄道コンテナを利用することが可能なのか。後編で考えていきたいと思います。